[ 2025/6/24 ]
梅雨の重だるさを予防する食べ物
梅雨時期の“重だるさ”を予防する食べ物 2019/06/04 05:32 ウェザーニュース 今年も既に九州南部まで梅雨入りし、関東や近畿も早ければ今週後半にも梅雨の時期を迎えそうです。 爽やかな初夏から一転、湿気たっぷりの蒸し暑い日々に、体や頭の重だるさ、むくみ、食欲不振、下痢といった体の不調も出やすくなります。東洋医学ではこの原因を、「湿邪」(大気中の湿気による不調)によるものと考えます。 今回、この湿邪を寄せつけず梅雨をスッキリ過ごすためのお勧めの食材を、源保堂鍼灸院の瀬戸郁保先生、瀬戸佳子先生に伺いました。 湿気による不調は、胃腸が弱っている時に起こりやすい東洋医学では、病気を引き起こすものを「邪気」といいますが、その中には、体の外からもたらされる「六淫」(風邪、寒邪、湿邪、燥邪、暑邪、火邪)と、体の内から生じる「内生五邪」(内風、内寒、内湿、内燥、内火)があります。 そのうち、梅雨の時季の不調の原因になりやすいのが、「湿邪」と「内湿」です。 湿邪とは、大気中の湿気が口や鼻、皮膚などを通じて体に入り、体の不調の要因となることです。「湿」には重い、ネバネバしている、停滞といった性質があるため、重だるさや頭痛、頭重、むくみ、湿疹といった症状をもたらします。 一方、内湿とは主に、乱れた食生活で胃腸(東洋医学では脾胃という)が冷えて湿気が溜ることで、体にさまざまな不調が生じることを指します。たとえば、食欲不振や下痢、軟便などです。 湿邪と内湿とは密接に関係し、両者が重なることで不調が生じるといえます。たとえば、湿邪が起こりやすい時季(梅雨など)に乱れた食生活を続けた結果、不調を起こす、あるいは内湿によって胃腸が弱っている時に、湿気の多い時季が重なり不調が生じる、などです。 いずれにしても瀬戸先生によると、「食生活の乱れによって脾胃が弱っていることが、この時季の不調の最大要因です。 |
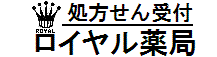







 ホームへ
ホームへ